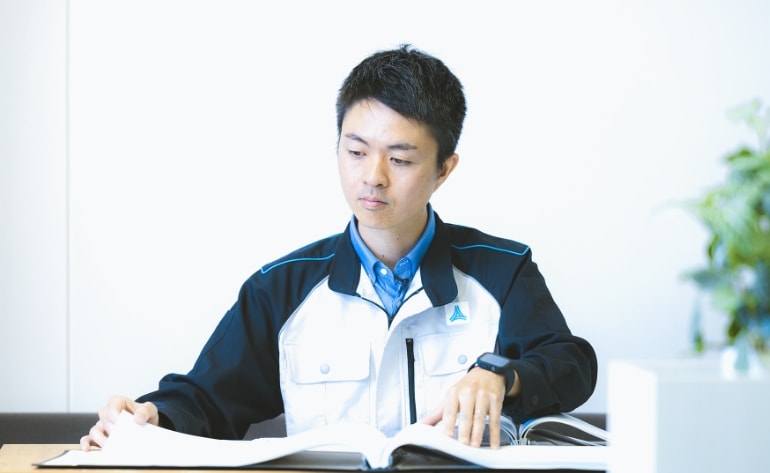K.ShinodaInterview

K.Shinoda
更新・建設局 日本橋プロジェクト設計課
都市環境科学研究科卒
2022年新卒入社
新卒入社
技術系総合職(土木)
2022入社
首都高速道路株式会社に入社。更新・建設局日本橋プロジェクト設計課に配属。トンネルの工事発注や関連する調査・設計業務を担当する。
仕事の大きさや構造物が密集する都心で人・
モノを運ぶ高度なネットワークに惹かれた
父が同業の会社に勤めていたこともあり、私も小学生のときから高速道路の見学会に参加するなど、道路という構造物を身近に感じていました。でも、学生のころは「大きなものをつくるのってカッコいいな」という漠然とした感覚しかなく「道路をつくりたい」というレベルでは考えていませんでした。
大学時代はゼネコンへの就職も視野に入れながら、「何をつくりたいのか」という点を絞り込んでいきました。私は社会インフラに興味があり、ダム・上下水道・港湾などの選択肢の中で、特に道路が面白いと改めて感じました。他の構造物とは異なり人やモノを運ぶネットワークをつくり、大都市だけではなく全国の人々の暮らしに日々関わっているという点に惹かれました。中でも都心の道路はとても狭い空間につくる必要があるので、技術的にもレベルの高い学びがあるのではないかと思ったんです。
また、私は大学で力学や基本的な構造の設計に加え、トンネル工学を学んでいたこともあり、日本橋エリアの首都高を地下化するプロジェクトにも興味がありました。「トンネルは安全面からも真っ直ぐつくるのが理想だけれど、あの入り組んだ都心にどうやってトンネルを通すのだろう」と疑問に思ったんです。都心の高速道路はほかにも難易度の高い設計が必要とされるため、大きなやりがいもあると感じて、入社を決めました。
新卒1年目から、針穴に糸を通すような
難しい更新プロジェクトに関われる
入社後から継続して、現在も日本橋区間地下化事業の設計課に所属しています。日本橋の首都高を地下化する本プロジェクトは3つのラインで担当を分けていて、私の役割は、主にシールドトンネルと開削トンネルの工事発注や調査・設計を行うことです。
日本橋区間地下化事業は、実はかなり難しいプロジェクトです。地下にトンネルを通す際、周囲や管の条件によりますが、ガスや水道を移設することはできます。一方、地下鉄は動かせません。その地下鉄の路線が、日本橋エリアには半蔵門線・銀座線・浅草線の3路線あって、その3路線をうまく避けてトンネルを設計する必要があります。また、安全に車両が通行できるように、道路の勾配や曲率は決まっており、通行可能な線形を維持しながら、障害物を避けていく必要があり、日本橋区間地下化事業は「針穴に糸を通すような工事」といわれています。さらに再開発事業で建物の建築工事が複数計画されていて、耐荷重の認識を誤るとトンネルが崩れてしまう可能性もあり、これらの条件から緻密な計算と調整が求められます。測量会社やボーリング会社と現場条件を調査する、材料メーカーと材料の条件を決定する、設計コンサルと構造物の条件や形状を決めるなど、様々な会社と協力して業務を進めています。
日々の業務に大変さを感じることはありますが、同時に嬉しさも感じています。正直、1年目は雑務が中心になるのかなと思っていたので、これほど大事な案件を新卒1年目で担当できるのはもちろん、任せてもらえる範囲も広いため、日々仕事のスキルが上がるのを感じています。

最新技術で課題を乗り越えていく。
歴史に残る工事ならではの魅力
日本橋区間地下化事業に関わってもうじき2年になります。最初は業務の全体像が見えず業務量の調整が大変でしたが、他のラインの先輩や同僚に分からないことを教えてもらう、上司に適宜相談する、といったコミュニケーションをきちんと取ることで、少しずつ業務コントロールができるようになりました。土木職の女性社員は男性社員に比べると少ないものの、社内では若手の成長を大切にする雰囲気があり、業務に集中して取り組むことができています。
また、日本橋区間地下化事業は厳しい条件下で地下化を成立させないといけないため、最新技術に触れるチャンスにも恵まれています。狭い空間をいかに上手く使うかが求められる事業だからこそ、それを実現するために最新技術を積極的に取り入れて、障害を乗り越えていくんです。任せてもらえる範囲が広いので、その分学ぶべきことが多く大変ですが、新しい技術を積極的に試していける楽しさもあります。
そして、私が関わった工事発注資料はこれから何十年もの間、さまざまな人の目に触れていくものになります。日本橋区間地下化事業に並ぶレベルの工事事例は少ないため、工事発注資料一つ取っても技術資産としての価値が高いと思っています。将来にわたって何度も見返されると思うと、歴史に残る仕事をしているんだと強く感じますね。2040年度の完成を想像しながら、着実に前に進んでいけたらと思います。
※所属・部署名等はインタビュー当時のものです


Schedule1日のスケジュール
09:00
出社
メールチェックを行い、一日の業務がスタート。
10:00
打ち合わせ
設計コンサルとの打ち合わせにて、設計条件の確認や構造物の設計を進めていきます。
12:00
お昼休憩
13:00
打ち合わせ
打ち合わせが短縮あるいはリスケになった場合、現場の状況確認を行うこともあります。
15:00
資料作成・確認
関係機関との打ち合わせの資料作成や、設計コンサルとの打ち合わせ資料の確認を行います。
18:00
退社
Day Offオフの日の過ごし方

私はアウトドア派で、普段からリフレッシュを兼ねてジョギングしています。
また、夏フェスに行ってバンドの音楽で盛り上がることもあります。
外で身体を動かしたり趣味を満喫することが非常に良い気分転換となっています。