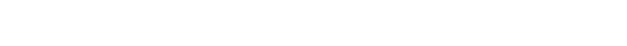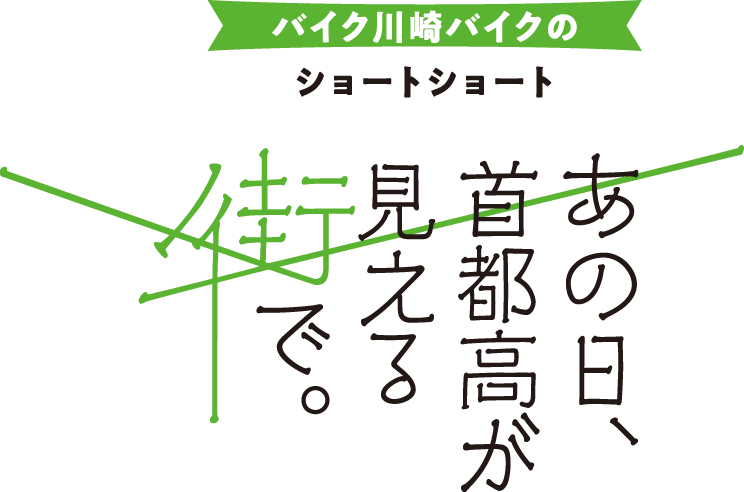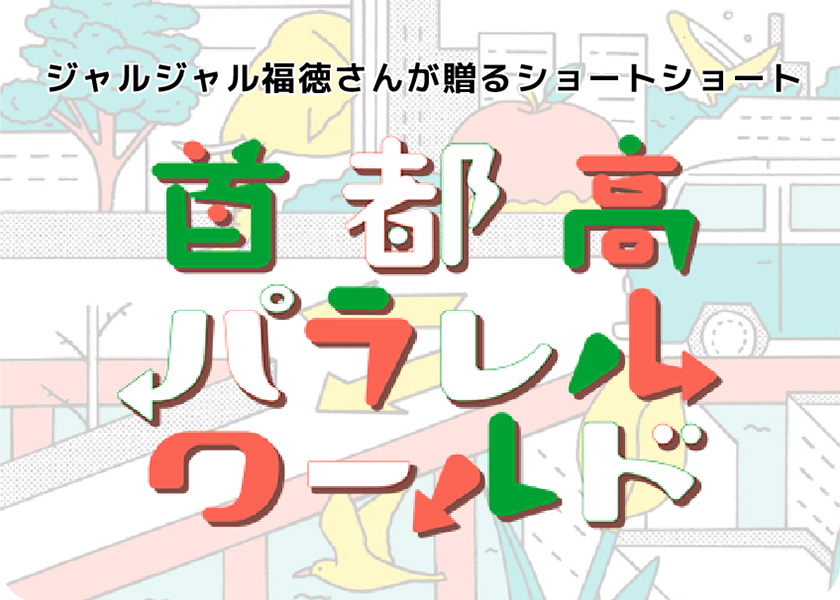TOP / バイク川崎バイクのショートショート あの日、首都高が見える街で。 / 第5回『円柱』
Column私たちが⽇々⽬にする景⾊に溶け込んでいる、東京の象徴とも⾔える⾸都⾼。
そんな⾸都⾼のある⾵景の中で暮らす⼈々のドラマを描いた超短編⼩説。

 首都高のある風景
首都高のある風景

![]() 高速神奈川1号横羽線
高速神奈川1号横羽線
横浜駅きた東口付近
(神奈川県横浜市西区)
みなとみらい線開通時にできた、横浜駅の「きた東口」を出ると、遮るものがないコンコースから、目の前を横切る横羽線を大パノラマで見ることができる。夕日が首都高に反射する時間帯が特におすすめ
第 5 回『円柱』
今日も横浜駅から始まるいつもの朝。いつものラッシュアワー。いつもの出勤時間に退勤時間。いつもの車両。いつもの人の波。いつもの夕暮れ。いつもの疲れ。
男はいつも通り、今日もいつも通り。
いつも通り、疲れていた。
男は今年で44歳になる。
長年勤務している会社は不動産関係で、とりわけブラック企業などというものではなく、それなりにやりがいのある仕事だった。
その身を会社に捧げてきた男は、生真面目すぎる性格もあってか独り身ではあるが、そこに引け目は特に感じてはいない。おそらくそのあたりの感覚は数年前に良くも悪くも麻痺したようだ。
年功序列の流れも手伝って、係長職についている男は、部下や上司とは付かず離れずの関係性。
いや、むしろやや離れてはいるかもしれない。
板挟みのポジションならではのストレスも抱え、常日頃から厳格な表情の男。
仕事が楽しいなどといった感覚はないが、不景気と言われ久しい昨今。食べていけてるだけでも恵まれているほうだとは思っていた。
しかし男は───疲れていた。
理由はなんとなくわかる。仕事とは“疲れるもの”だから。生きていくためには楽はできない。仕方のないこと。
その日、男が満員電車から降りたとき踵を踏まれた。よくあることだ。反射レベルで振り返るも、人混みに紛れた悪意のない所業は誰が行ったのかもわからない。ふと、革靴の汚れが気になり足元に目をやると、誰かと肩が軽くぶつかった。
「あ……すみませ……」
見上げるともう誰もいない。
謝る隙も与えられず、過ぎ去る人。
眉間にしわをよせ早歩きする人。
大きなヘッドホンを耳にはめスマホを眺め、のろのろと歩く人。
どこを切り取っても、いつもの疲れる風景。
この負のルーティンが一生続くのかと思うと背筋が凍った。休みの日や、たまの贅沢な晩餐で英気を養えばいいなどとよく言うが、割に合わない。
趣味に乏しく、人生に明るさを見いだせない独り身の男は憤っていた。
明らかに比率がおかしい。疲れる時間のほうが圧倒的に長い。皆、生きていくためだけに、生きているのではないか。
「はぁ……」
この横浜駅の朝はもちろんだが、帰宅時のラッシュもなかなかのものだ。
男は混雑率150%の湘南新宿ラインから、自宅のある横浜駅に降り立つ。
「ふぅ……」
疲れきった男はいつも通り、二度、ため息を吐いた。
日中、少量の雨が降っていたが、やんでいたことだけがこの日の救いだった。
そしていつも通り、重い足取りで家路へと───とはならなかった。
あまりにも帰宅ラッシュを避けたい衝動から男は、人のいない、ただ人のいない方向へと歩いた。
それは特に前向きな行動などではなく。
いわゆる本来の出口とは違い、結果、逆方向の出口へと向かう男。そこに強い意思などはなかった。
ただ無意識的に、ただ散文的に。
「ん……?どこだここ……?」
男は気がつくと、横浜駅のきた東口に辿り着いた。
最寄りの駅ほど、実は決まりきった出口しか使わないもの。勝手知ったる場所と思い込んでいた男にとって、この景色は初めてだった。
慌ただしく人々が行き交ういつもの出口とは違い、眼前に広がるのは赤々とした夕日と、そこにそびえ立つ首都高の風景。
雨上がりの夕暮れはどこか儚く、無骨ながらも人間の叡智の結晶ともとれる、堂々たる首都高の存在感。
なぜか男は目が離せなくなった。
まるで子供の頃、寄り道をしたら自分だけの秘密基地を見つけたような。いつもの帰り道が違って見えたあの感覚。
「これは……すごいなぁ……はぁ……」
決して“それ”は美しいスポットであるとか、人の心を動かす情景の類などではない。しかし、男のため息が、感嘆の吐息に変わっているのは間違いなかった。
そこから男はふと、駅出口付近にある太く丸い柱に目をやる。すると、子供の頃に好きだった担任から言われたある話を思い出した───。
「……円柱ってね、おもしろいのよ」
「おもしろい……?」
「うん。見て。ほら普通に見てたらただの円柱。でもね、真横から見ると……ほら、なんの形に見える?」
「あ、長方形!?」
「そう。で、真上から見ると……?」
「まん丸!」
「その通り!こんなにも見る角度によって変わる物がある。それはつまりね、なんでも、いろんな角度から物事を見るとおもしろいよ、ってこと」
「へー!」
───子供の頃に、なんとなく聞いていた円柱の話。まさに、同じ駅でも見る場所によってはこうも違うのかと数十年ぶりに実感する男。
さらに真横に目をやると、女子高生がスマホで夕暮れと首都高の写真を何枚も撮っていた。
その表情はとても生き生きとしている。
もしかしたら、彼女も“この場所”を初めて見たのかもしれない。もちろん、それを確認などはできないが。
一つ言えることは、男にとっての今日は、いつもの今日とは違ったということ。
*
あれから男は“角度を変えて物事を見る”ことを意識した。
とはいえ、いきなり様々な物事の角度を変えるのは難しい。元々厳格で寡黙な男がおいそれと変わることはできない。
故に、まずは一つだけ角度を変えて、仕事に取り組むことにした。
「峰山くん。ちょっとこの書類なんだけど」
「あ、はい」
「ここの物件はまだ空きってことだよね?」
「ええと……これは……はい。そうです」
「うん。ありがとう」
「いえ……」
「ん?どうした?」
「いや、係長なんか最近、雰囲気変わりました?」
「…雰囲気?」
「なんか丸くなったというか表情が穏やかになったというか……あ!すみません!変なこと言いました! 」
「ははは。いやいや、大丈夫」
男は、常に下がっていた口の角度を変え、常に上げてみることにした。まずはその一つだけ。ただそれだけのこと。
慣れない表情はこれまた疲れるが、この疲れは悪くないなと、男は思った。
【完】
この物語はフィクションです。

次回のショートショートは9⽉1⽇更新予定です