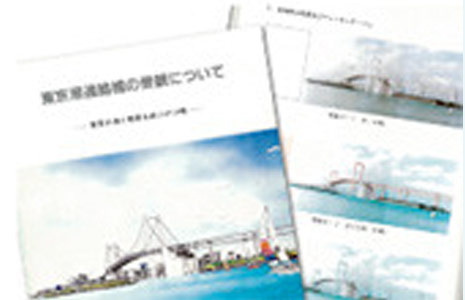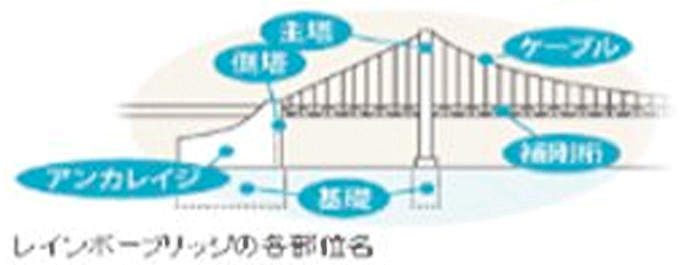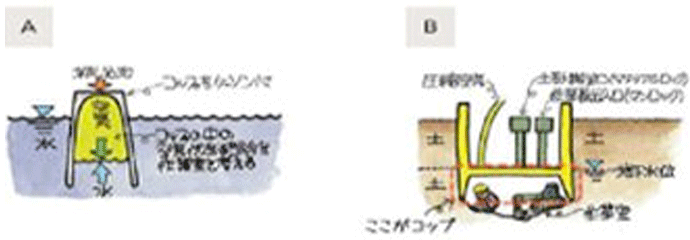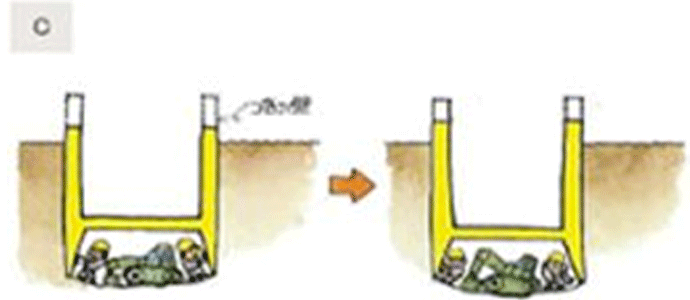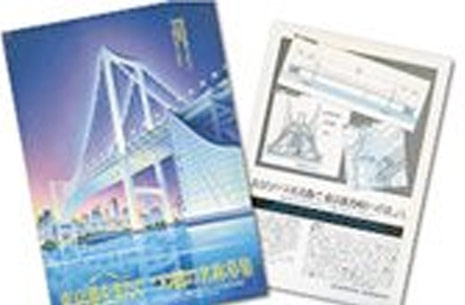- 首都高道路交通情報
- 料金・ルート案内
-
首都高を使う
- 首都高ネットワーク案内
- パーキングエリア
- 駐車場
- 便利な使い方
- 安全走行のために
- 交通安全対策
- 事故多発地点マップ
- 首都高を安全に走るためには
- 江戸橋ジャンクションから箱崎ジャンクションまでのご利用案内
- 小松川ジャンクション・中環小松川入口のご利用案内
- 大井ジャンクション・大橋ジャンクションの分岐案内
- 横浜青葉・横浜港北・生麦ジャンクションのご利用案内
- 板橋・熊野町ジャンクション間、堀切・小菅ジャンクション間の走り方のポイント
- 大橋ジャンクションの運転に注意
- 馬場出入口のご利用案内
- 大井入口・中環大井南入口のご利用案内
- 山手トンネルでのドアミラー等くもりの発生について
- 事故・故障のときは
- 冬季期間の首都高のご利用にあたってお客さまへのお願い
- 首都高速道路への歩行者や自転車等の進入禁止
- 首都高のトンネル防災
- 大地震が発生したら
- 首都高上の車両規制・通行規制
- 料金・ETC・割引情報
- 首都高を知る・楽しむ
- サイトマップ
CLOSE


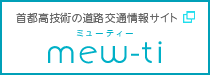
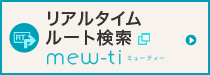
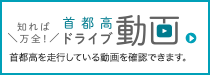
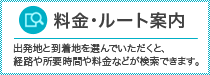
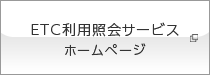

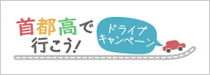



 橋のデザインができるまで
橋のデザインができるまで